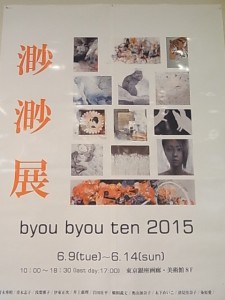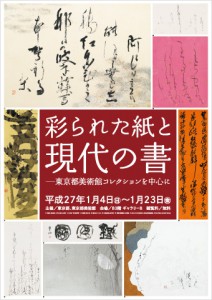カテゴリー別アーカイブ: 展覧会•イベント
花と器のハーモニー2015
横浜•山手西洋館で「花と器のハーモニー」というイベントが
行われています。
毎年このイベントにはボランティア撮影隊として行っていましたが、
今年は予定が合わず、見学を断念しました。
友人から情報が入りましたので、ご紹介したいと思います。
どの館も個性的で楽しめる内容となっているそうです。
また例年にはない飾り付けで、見応えがあるとのことです。
この週末で終了になりますので、お時間ありましたらお出かけ下さい。
日本画展を見る
友人が参加している日本画のグループ展を2つ、見てきました。
まずは女性8人による「こころばえの会」です。
それぞれ画風が異なるものが、画廊の中で融合している様が
心地良い展覧会です。
友人の斉藤佳代さんの作品です。
彼女の作品については以前もご紹介させて頂いていますが、今回は
植物をモチーフに優しいタッチで描いています。
清々しい色合いで、本当に心が和みます。
斉藤さんと他の作家さんの作品です。
個性の違いが融合しているのが、おわかり頂けるでしょうか?
私は下段右の斉藤さんの作品「梅花ウツギ」がとても気に入りました。
会期は13日(土)までです。
居心地のよいギャラリーですので、それも含めてご覧頂けたら
幸いです。
もうひとつが「渺渺展」です。
こちらは若手作家さんのグループ展で、個性のぶつかり合いが
面白い展覧会です。
同じ日本画材を使っていながら、これほど表現の幅があるのかと、
いつも感心させられます。
友人の廣瀬佐紀子さんの作品です。
彼女の作品は、ダイナミックな構図が魅力です。
シンプルが故に伝わってくるものもストレートだと思います。
2つの展覧会は、毎年6月に会期を重ねるように開催されます。
雰囲気が違い、それぞれ刺激を受けるものが大きいのでハシゴする
のを楽しみにしています。
渺渺展は14日(日)までです。
銀座にお出かけになるようでしたら、是非2つともご覧下さい。
原稿あり
明日はセブンカルチャーセンター成田教室で、体験講座を
行います。
まず金繕いの歴史についてお話する所から始まるのですが、
これには原稿を用意してあります。
緊張しやすい質なので、舞い上がってお話する内容が飛んでしまわない
ように準備してあります。
何回か行っている講座なので、毎回推敲し、書き込みがたくさんあり
ます。
また想定される質問の回答も盛り込んでありますので、情報量が
豊富なのです。
ちなみに右下に写っているのが、プロジェクターに映される画像です。
これも興味深い資料をご用意しています。
今夜は再度リハーサルをして、休みます。
よりよい講座になるよう、頑張ります!
体験会 準備完了!
TOPの新着情報やブログでお知らせしてきましたセブンカルチャー
クラブ成田の体験会の準備を行いました。
すでに何回か行っているイベントなので、準備もこなれています。
回数をこなすたびに、いろいろ改良も加え、より楽しんで頂ける
ように工夫しています。
このところテレビで金繕い(金継ぎ)が取り上げられ、教室でも
その話題が出ていますが、改めて金繕いとは何なのかというのは
なかなか講座の中ではお話する機会がありません。
そのような教養部分あり、金繕いの技法をお話する実践部分ありに
加え、蒔絵体験もできる講座です。
まだ受付可能ですので、ご興味がおありでしたら、ご参加下さい
ませ。
日時:6月1日(月) 10:30〜12:30
ボッティチェリとルネサンス展
現在渋谷•Bunkamuraミュージアムで開催されている「ボッティチェリと
ルネサンス」展に行ってきました。

ボッティチェリというと「ヴィーナスの誕生」が有名ですが、今回の
展覧会は副題に「フィレンチェの富と美」とあるように、ルネサンスの
原動力となった銀行•金融業と近代のメセナ活動の誕生をボッティチェリの
名品とからめて紹介しています。
この時代の絵画は、テンペラと呼ばれる顔料を卵白で溶いて細筆で細い線を
重ねて描く技法や、フレスコというしっくいが乾く前に顔料を水で溶き、
描いていく特殊な技法が行われていました。
上の画像はフレスコ画の「受胎告知」です。
フレスコ画は、その日描く分だけしっくいを塗り、描き直しも出来ない難しい
技法です。
それでこれだけのものを完成させるというのは、相当の技量がなければならない
というのがわかります。
展示されている他の画家と比べると、やはりボッティチェリは、その優美さと
清麗さが抜きん出ています。
このように技法の難しさ、時代背景を理解した上で見ると、西洋美術を勉強
してきたつもりになっていたことに気がつきました。
これからは新たな目で見ていきたいと思います。
明日館の桜2015
自由学園 明日館は、建築の巨匠フランク•ロイド•ライトの設計の
建物で、洋館好きとしては一度は訪れたいと思っていた場所でした。
それが今回、桜見学会のイベントにお誘い頂く機会を得ました。
道路から桜越しの明日館です。
ライトアップされた桜と、明日館の取り合わせは本当に美しかった
です。
桜は、ソメイヨシノ3本と大島桜(手前から2本目)の計4本です。
わずか4本、されど4本。
この敷地に建物とのバランスを考えると、4本の桜がベストマッチです。
ホール内部から桜の臨んだところです。
明日館を象徴するライト設計の窓と桜のコラボレーション。
この日のメインイベントです。
一般には入れない事務所に入れて頂き、内部の照明を消して撮影させて
頂きました。
窓越しに見える夜桜は妖艶という言葉がぴったりでした。
次の機会には、ライト建築のデザインをご紹介したいと思います。
彩られた紙と現代の書
すでに23日で終了してしまったのですが、東京都美術館で
催されていた「彩られた紙と現代の書」展に行ってきました。
この展覧会は「紙」に注目し、書をしたためる紙の中でも、華麗な
装飾を施した「装飾料紙」の世界を紹介した展覧会です。
ちょうど墨流しなど料紙の制作をしていたところでしたので、タイムリー
な展覧会でした。
上の画像で右下に写っているのが仲田光成先生の作品です。
私は表書きのお手本として、仲田先生の書を頂いているのですが、実に
気品があり優美な書です。
書を書くならこうありたいという、あこがれでもあります。
今の実力では散らし書きなど夢のまた夢ですが、何とか時間を見つけて
努力は続けたいと思っています。
世田谷ボロ市2015.1月
例年12月に行っている世田谷ボロ市ですが、スケジュールの都合で
行けず、1月の回が開催された今日、足を運んでみました。
しかし雨、風とも強い荒天。
16時くらいに着いたのですが、ほとんどの店が畳んでしまって
いました。
それでも開いていた数店の中から、修復が出来る器を購入して
きました。
3点とも欠けやヒビがあり、それぞれ200円と格安です。
たまたま全て紙型印判ですが、いずれも柄が緻密で綺麗なので選びました。
まずは汚れを取って、修復にかかります。
何かの参考になるようであれば、教室にお持ちするかもしれません。
世田谷ボロ市の1月の回は、明日も開催されます。
明日は天候が回復するようですので、興味のある方はお出かけ下さい。
シンデレラ•ツリー
今日は原一菜先生のNHK文化センター横浜教室の助手の日
でした。
横浜教室のあるランドマークプラザではディズニーのシンデレラを
モチーフにした「シンデレラ•ツリー」が飾られています。
ガラスの靴やカボチャの馬車があしらわれているようです。
今ではライトアップされたツリーは珍しくありませんが、ランドマーク
プラザのツリーは特別のような気がします。
香水塔の修復
先日からレポートしている庭園美術館の香水塔について、今回の
修復過程の興味深い点について書いてみたいと思います。
このオブジェの白い弾丸状の部分と上の渦巻き部分は、フランスの
国立セーブル製陶所で作られています。
弾丸状の部分は庭園美術館として生まれ変わる前に破損し、かなり
バラバラに割れてしまっていました。
以前の修復で形状は戻されていたものの、ひび割れがひどくなり、今回
改めて修復されました。
この修復を担当されたのが西洋の古陶磁器修復を行う工房いにしえの
佐野智恵子さんです。
佐野さんはイギリスで専門教育を受け、「カラーフィル」という方法で
修復をなさいます。
これは元の陶磁器の色•透明度•質感を合わせたパテを埋め込む方法で、
再修復もしやすいのだそうです。
ここに日本の金繕いとは文化の違いがあります。
陶磁器が後の世代に伝える文化財と捉え、表面的には全くわからない
ように修復し、数十年後、数百年後の再修復にも備えるのがイギリス
の文化なのです。
(食器としては使用出来なくなります。)
それに対し、日本の金繕いは使う為に直すのが第一義となります。
これはTOPページの記事にも書きましたように、持ち主のステータスとして
茶席に出すのが大事だったからです。
また繕った状態も景色として尊びました。
香水塔は細かい破片に割れてしまっているなどとは、全くわからない
ように修復されています。
この角度から見るとミミズ腫れ様の線が数本見えるくらいです。
香水塔自体の美しさとともに、それを拝見することを可能にして
くれた高い技術をご覧頂きたいと思います。