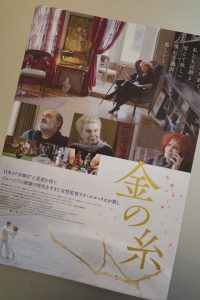NHK文化センター柏教室のTさんの作品をご紹介致します。
ピーターラビットのマグカップの取手が根元から折れて
しまったものです。
根元から折れてしまった場合は内側まで穴を貫通させ補強する
必要があります。
かなりな「大工事」になるので怯む方がほとんどなのですが、Tさんは
挑んで下さいました。
内側にどうしても補強の痕跡が出てしまうのですが、上側はピーター
ラビットに掛けてニンジンの形で蒔絵されました。
このようにキチンと補強すれば根元から取手が折れてしまっても再び
使用が可能になります。
恐れずチャレンジして頂ければと考えています。