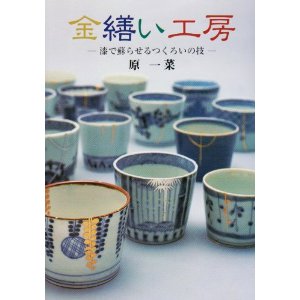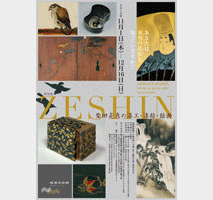月別アーカイブ: 2012年12月
原一菜先生の著書
いくつかのお教室ではご紹介しておりますが、金繕いの教室は
原一菜(はら いちな)先生の著書『金繕い工房』に準拠して
行っております。
この本は教室でお教えしている内容の補完になるばかりでなく、
金繕いの歴史や、上絵付けの文様の考え方など、技法書というより
教養書と言える濃い内容になっております。
ご理解頂きたいのは、本の説明は教室でご説明しているより安全を
みた方法で解説されているということです。
これは 技術という物は本来口伝で伝承されるものですので、本のみ
ご覧になって金繕いを試みられる方には、そうせざるを得ないからです。
教室にご参加頂いている方には、それぞれ直したい器に合わせて
より詳しく手順•コツなどお話しています。
なお大変申し訳ありませんが、この本を教室で販売してはおりません。
書店•ネットなどでご購入頂ければ幸いに存じます。
(出版社:里文出版 価格:¥2,625)
※私共一菜会としては『金繕い』が古来からの本筋の言葉と
考えております。
金継ぎとは、近代に発祥した金繕いと同じ意味の言葉です。
大物!
千葉教室Yさんの作品を、ご紹介します。
アフガニスタン産の大理石の器です。
40cmほどの径で、重量もかなりある大物です。
割れて いたのを接着し、欠損部を補ったのですが、透け感のある石
なので、ガラスの修復の技法を応用しています。
なかなか欠損が埋まらず、仕上げの線も長いので、Yさんはかなり
苦労されました。
しかしこうして完成に辿り着きますと、圧巻です。
ご本人はまだまだの感じでおられますが、大らかな線が器の
大きさに合っていると思います。
このように仕上げは、器の雰囲気に合っていることが重要だと
考えています。
急須の補強
大宮教室Iさんの作品を、ご紹介致します。
急須の注ぎ口の補強をして頂きました。
華奢な注ぎ口が、折れてしまっていました。
これを接着しただけでは、使用上の不安が残ります。
皆様ご経験があると思いますが、突出している部分はぶつけやすい
からです。
そこで接着したあと補強し、仕上げをして頂きました。
Iさんは仕上がりがどのようになるのかご不安だったようですが、
完成してみてビックリ!
見違える姿に喜んで頂きました。
このブログで何度もお話しているように、銀はこのあと硫化して
いきます。
本体のマットブラックの釉薬に馴染んでくるでしょう。
カリンのハチミツ漬け
原一菜(いちな)先生からカリンを頂きました。
のど飴などでカリンの名前は知っていましたが、実として
見るのは初めてです。
これでハチミツ漬けを作ります。
大きくカットしたあと、細かく切り込みを入れてハチミツに
漬け込むだけです。
薬効があるので、種も投入しています。
一昼夜漬けただけで、かなり水分が出て完成します。
これをお湯で好みの感じに薄めて飲むと、のどの痛みに効きます。
講師としては声が出なくては仕事になりませんので、この冬は
頼りにしようと思っています。
筆の洗い方•保管方法
金繕いの教室で、よくある質問のひとつが筆についてです。
洗い方ですが、まず薄め液で漆を落としたあと、中性洗剤でしっかり
洗います。
この時のポイントは、洗剤の泡を穂先に含ませるように揉み込む
こと。
引っ張ったり、折ったりすると、穂先が 少なくなる原因になります。
その後濡れている内に穂先を整え、サックに入れます。
筆立てに立てて乾燥させれば、完了です。
サックは筆にもともと付いていたものを使うのがbestですが、
無くしてしまった場合には、ストローやビニールチューブで
代用します。
穂先を大切に扱うのが肝心ですから、持ち運ぶ際にも注意し、
曲がったり、乱れたりしないようにしましょう。
メジャーリーグのイチロー選手ではありませんが、道具の
コンディションは、美しい仕上がりの第1歩です。
市川教室 15:30〜クラスのみなさまへ
本日は教室中に地震が発生致しまして、さぞ驚かれたことと
思います。
しかし皆様 が大変落ち着かれていたこと、改めて御礼申し上げます。
またラジオを携帯されている方がおられるなど、日頃の防災意識の
高さが伺えました。
東日本大震災以降、NHK学園様を始め、各カルチャーセンターでは
避難誘導など責任をもって行うよう徹底しておられます。
どうぞ今後も安心して受講頂きますよう、お願い申し上げます。
大宮教室 ご連絡
大宮教室の「金つぎ•銀つぎ」講座を受講して下さっている方に
ご連絡申し上げます。
既にご承知の方もいらっしゃるとは思いますが、来月12月の講座は
第4月曜日が祝日になるため、第2月曜日の10日に振替して行います。
師走のお忙しい時期ではありますが、お間違いなくご参加頂ければ
幸いです。
※よみうりカルチャー様の講座については、「金つぎ•銀つぎ」という
講座名になっております。
“金継ぎ” は、近代に発祥した金繕いと同じ意味の言葉です。
トクサ
トクサは、漢字で「砥草」「十草」「木賊」と書きます。
スギナの仲間で、非常に繁殖力が強く、水さえ十分に与えれば
虫害に合うこともありません。
金繕いの教室でご提供しているトクサは、このように育てています。
(何度も植え替えしているので、根があちこちに向いてしまい、
真っ直ぐ伸びなくなってしまったところが残念です。)
11月から翌年2月くらいまでが、刈り取り時ですが、私は年末には
刈り取る予定です。
よくご質問を受けるのが、生えている状態で枯れた先を道具として
使えるかということです。
このような状態ですね。
これは残念ながら使えないのです。
実際使って頂ければわかるのですが、脆く崩れてしまったり、
まったく削れなかったりと用を成しません。
使えたら乾燥の手間がかからなくてよいのですが、やはり楽して得られる
物はない、ということでしょうか。
刈り取って1週間も天日に干せば使えるようになりますので、是非
ひと手間かけてみて下さい。
柴田是真の漆工•漆絵•絵画
根津美術館で行われている柴田是真の展覧会に行って
きました。
柴田是真は江戸末から明治初期の漆芸家で、青海波塗りなどの独自の
技術を持つ技巧派ですが、その技術には四条派の絵画を学んだ画力が
バックボーンにあります。
漆工の技術が素晴らしいのはもちろんですが、私は滑稽洒脱な絵画に
是真の温かな人柄を感じています。
山手西洋館 クリアファイル
昨日ご紹介した横浜•山手西洋館で販売しているクリアファイルです。
美しい西洋館の立面図をあしらったデザインになっています。
色は乳白色に図版が黒(左)と、横浜ブルー地に図版が白(右)の
2色があります。
実はこのクリアファイル、山手西洋館さんから依頼を受けて、
私がデザインしています。
あまり画像が上手に撮れなかったので、山手西洋館にお出かけの
際には実物を確認して下さると嬉しいです。